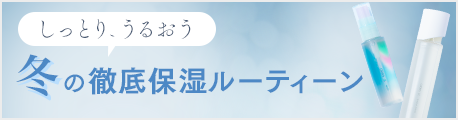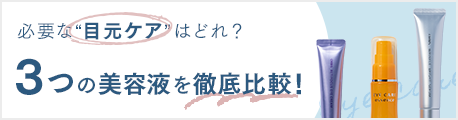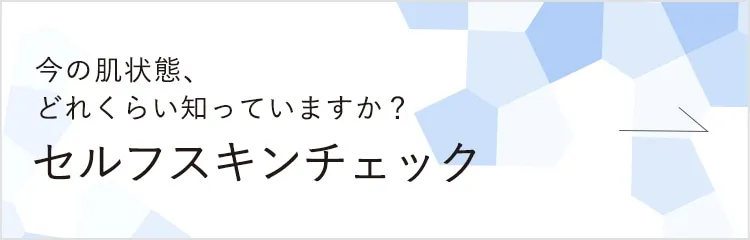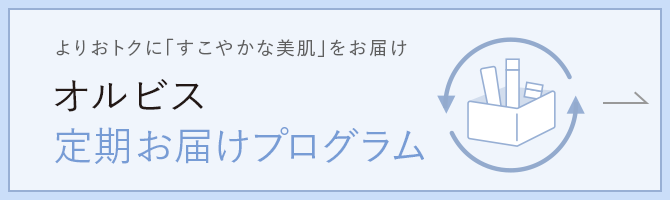池田重子|時代を生きた女たち#137
裕福な家庭で育ち、おしゃれが大好きだった少女が、相応な家に嫁いだものの、40歳を前に夫と別居。娘2人を抱えて、どう生きていくか、頭の中が真っ白だった。だが40代で人脈を切り開き、それに導かれるようにして、50 歳で古裂の店を開いた。そして旧財閥の夫人が残した帯留のコレクションに出合い、大きく運が開いたのだ。
- 池田 重子(いけだ しげこ) ●1925〜2015年
-
優れた感性で着物の魅力を広めた和装コーディネーター
大正年間から昭和初期にかけて、日本の伝統文化は、一つの頂点を迎えた。和装の世界でも、職人の技術や感覚が研ぎ澄まされ、それを高く評価する富裕層も存在した。
池田重子は主に、その頃の着物や和装小物を収集した。膨大なコレクションの中から、この着物には、この半襟に、この帯で、この帯留とこの髪飾りと、優れた感性でコーディネートして、雑誌や展覧会などで発表した。
それぞれ出どころの異なるものが、池田重子の手に引き寄せられ、まるで最初から揃いで誂えたかのように、見事に調和したのだ。
50代こそが最適な時期
池田重子は大正14年に横浜で生まれた。祖父の鈴木弁蔵は農家の生まれで、年端もいかないうちから米穀商に奉公に出たが、勤勉で才覚があり、外米の輸入で巨万の富を築いた。
父は米の輸入を引き継ぐかたわら、株を売り買いし、裕福な暮らしぶりだった。上質な結城紬を着こなし、骨董を趣味とした。
重子は7人きょうだいの次女だったが、幼い頃から骨董好きで、1人だけ父親に骨董市に連れて行かれた。小学生ながら中国骨董が気に入って、重厚な衣装箱を買ってもらったという。また芝居や芸者遊びの宴席にもついて行って、粋な世界にも触れた。
京都の公家文化から続く華やかさではなく、江戸の武家文化を引き継ぐ、一見地味ながらも凝った美しさ。それが重子の感性を育てた。
だが10歳のときに二・二六事件が起きて、株が暴落。以来、暮らしは少しずつ陰り始めた。戦争中は贅沢が禁じられ、戦後まもなく父が他界。
そんな中、重子は22歳で見合い結婚した。相手は早稲田大学政治経済学部を卒業し、明るくおおらかな人柄で、印刷業を営んでいた。しかし酒を飲むと、おおらかさが災いして人に奢ってしまう。稼業が上手くいかなくなると放蕩に奔った。
夫婦の間に溝が広がり、重子が39歳のときに別居。娘たちの養育費は受け取ったが、それだけでは充分に暮らしていかれない。一時は、どうしたらいいか途方に暮れた。
ただし重子は、やわな令嬢育ちではなかった。何かしなければならないときには、とにかく走り出す。祖父から受け継いだ商魂があったのだ。
料理が得意だったので、とんかつの店を出そうと目論んだ。魚は目利きでなければ仕入れができないが、とんかつなら、いい豚肉があれば何とかなるし、材料の無駄が少ない。そう考えてソースの美味しい店で修業を試みた。しかし店の女将に「人には器ってものがある。あんたはとんかつ屋をやる顔じゃないよ」と諭されて諦めた。
一方で、美々(みみ)の会という趣味人の会合に参加した。もともと東京藝術大学出身の音楽家の集まりだったが、重子は音楽にも造詣が深かったし、サロン的な雰囲気が魅力だった。そんな音楽会や食事会などで「洋服を着ていると、ただの人に見える」と言われて、和服を着るようになった。
そこで知り合った繊維会社の重役から、意外なアドバイスを受けた。以前から重子は紅型(びんがた)やろうけつ染めを習っており、参考のために古裂(こぎれ)を集めていた。それを屏風に貼って作品にしてはどうかと勧められたのだ。
屏風など作ったことはなかったが、重子は幼い頃からつちかったセンスで、たちまち洒落た屏風を23点も制作した。さらに、その重役の口利きにより、新宿の百貨店で「時代布屏風展」という個展を開催。決して安くない作品だったが、驚いたことに完売した。
後年、重子は自伝を出版したが、その中で「何かを始めるとき、自分を引き上げてくださる方が現れたら、それは上手くいくでしょう。自分がその仕事にふさわしいと、人さまが認めてくれたということです」と書いた。
続いて「世界の染織展」という百貨店の催しに誘われて、残っていた古裂を出品したところ、これも驚くほど売れた。売るものがなくなると、重子は催事場の裏で、自分が着ていた長襦袢をほどいて切り分け、さらに自宅の布団のガワまではいで、布をかき集めた。
この体験によって、持ち前の商魂に火がついた。もともと骨董好きだったために、骨董商も視野に入れて鑑札を取っていたが、相当な開業資金が必要だし、贋作をつかまされる懸念もあって、二の足を踏んでいた。でも古裂なら自信があった。
そこで目黒の住まいから遠くない場所に、古裂の店を開いた。そういった専門店は、古くから京都にはあったが、東京にはなかったのだ。
店番を姉妹に任せ、自身は古裂の大荷物を抱えて売りに歩いた。特に人形作家のもとに行くと、お弟子さんたちも集まって、次々と買ってもらえた。
歩いて帰宅できないほど疲れ切るまで働いた。もう50代に入っていたが、重子にとっては最適な時期だったという。40代では、まだ余裕があって真剣にはなれないし、60代では体力が衰えるからと、自伝に書いている。
家の代わりに帯留を買った
そんな頃に骨董オークションに出かけたところ、旧財閥の夫人が高齢で亡くなって遺品が売りに出されていた。ゴージャスなファーコートや素晴らしい着物が登場する中、重子の目は帯留のコレクションに釘づけになった。亡くなった夫人が吟味して集めたものだけに、どれも小さな芸術品だった。
このとき重子は、まとまった金を持っていた。夫と別の女性との間に生まれた子どもが、幼稚園に入るのを機に離婚が成立。家を買うようにと、慰謝料を受け取っていたのだ。
それを注ぎ込んで、帯留のコレクションを、すべて買い取った。ためらいはなかった。元気で働けば、いつでも家は買える。でも、このコレクションには2度と出合えない。散逸させてはいけないと直感したのだ。
ときは昭和50年代初め。和服を着る人が減っており、着たとしても白い半襟で、帯締めは固く結ぶだけ。帯留を使う人などいなかった。
でも帯留のコレクションを手にするや、かつての母たちの装いや着こなしを思い出した。刺繍や色半襟がのぞく襟元。季節ごとの帯留や髪飾りの使い分け。そんな記憶に誘われ、アンティークの着物や小物を求め始めた。
専門の競り市に出かけると、箪笥ごと売りに出されることがあった。だが、いちいち引き出しを開けて中を確かめていたら、ほかの人に競り落とされてしまう。
そこで重子は引き出しに手を入れ、結城紬が指に触れたら、即座に箪笥ごと買った。父が愛用していて感触を知っていたし、結城紬があるなら元の持ち主の感覚がいいはずで、ほかの品物も確かだったからだ。
当時の古着は清潔感に欠けたが、汚れやほころびを徹底的に手入れして、目黒の店に出した。いよいよ店は繁盛し、同時に協力してくれる人に恵まれて、みずからのコレクションも充実していった。
そんなコレクションの中から、大正時代の着物を5点、コーディネートして、若い女性向けファッション誌に掲載すると大評判になった。着物離れと言われて久しかったが、若い世代は和装を求めていたのだ。
着物の専門誌にも連載ページを持ち、百貨店などでの展覧会も人気を博した。新作着物のデザインも手がけたし、刺繍や色半襟を流行させたのも重子だった。
着物には素材や柄による格式や、季節や着る場面などに決まりごとがある。そんな制限を踏まえたうえで、ぴたりと合うものを探し出す楽しさを、重子は89歳で亡くなるまで追求した。
参考資料/池田重子著『遅く咲くのは枯れぬ花』、『池田重子 美の遍歴』など
取材協力/時代布と時代衣裳 池田
Profile
植松三十里
うえまつみどり:歴史時代小説家。1954年生まれ、静岡市出身。第27回歴史文学賞、第28回新田次郎文学賞受賞。『時代を生きた女たち』(新人物文庫・電子書籍版のみ)など著書多数。
最新刊は『家康を愛した女たち』(集英社文庫)。
https://note.com/30miles